介護職の給料アップは2024年度改定に期待!物価高騰で3割の事業所が賞与・昇給見送り
物価高騰の影響で介護施設・事業所の27.3%が昇給・賞与の減額・見送りを実施
介護人材政策研究会が調査結果を発表
2023年3月、一般社団法人介護人材政策研究会が、全国1,277の介護施設・事業所を対象に、物価高騰の影響を調べるアンケート調査を実施。先日、その結果が公表されました。
それによると、物価・光熱水費などの高騰による影響については、「大いにあった」が50.74%、「あった」は35.16%。合計で9割近くに上りました。ほとんどの介護施設・事業所がコスト高に直面している実情が分かります。
また物価・光熱水費などの高騰への対策として、92.62%の介護施設・事業所が「節電・物品の節約等」を行ったと回答。さらに47.38%が「預貯金等の取り崩し」、27.3%が「昇給や賞与支給の減額・見送り」をしたとの回答が得られています。
ここで注目すべきは、昇給・賞与支給の減額・見送りをした介護施設・事業所が3割近くに上っているという点です。世間的にはマスコミなどで、物価上昇に合わせて賃上げをすべきとの論調が盛んに行われていますが、介護業界では、3割近くの介護施設・事業所で減給・賞与見送りが生じているわけです。

急激な物価上昇の現状とは
ロシアによるウクライナへの侵攻、急速な円安の進行、世界的な原材料価格の高まりにより、国内では水道光熱費や食料品などの物価高騰が続いています。
消費者物価指数は2022年9月に前年比3.0%上昇。消費税率上昇の影響を除外すると、物価が前年比3%を超えるのは1991年8月以来、31年1カ月ぶりのこと。当時はバブル経済の余波のある時期で、今の物価高とは性質がまったく異なるともいえます。
介護施設でも深刻な影響が出ています。福祉医療機構が介護施設を対象に行った全国規模の調査によると、2022年の上半期の段階で、「原油価格・物価高騰の影響を受けている」との回答割合は88.5%に上っていました。
また、2022年度上半期の経費が前年度比で5%以上増加すると回答した介護施設は、調査対象の48.9%に上っています。
こうした状況の中で、昇給や賞与の見送り・減額にまで踏み切った介護施設・事業所が登場しているわけです。
介護施設・事業所における物価高騰の影響の実情
物価高騰の影響により事業の廃止、倒産の恐れのある介護施設・事業所が約3割
冒頭で紹介した一般社団法人介護人材政策研究会の調査結果によると、「物価・光熱水費などの高騰を受けた今後の事業継続について」の質問では、27.38%が「このままでは、数年で事業の廃止や倒産に至る可能性が」あると回答。危機的状況に陥っている介護施設・事業所が3割近くに上っている実態が明らかにされています。
この実情は、倒産件数としても現れています。東京商工リサーチの調査によると、2022年度における「老人福祉・介護事業」における倒産件数は前年比76.5%増となる143件。これは介護保険制度が始まった2000年以降で最多件数です。
内訳は訪問介護事業所が36件、デイサービス・ショートステイが45件、有料老人ホームが10件、その他が9件。老人ホームなど入所施設は少なめですが、特に在宅系の介護事業所の倒産が深刻化しています。
しかし介護人材政策研究会の調査結果を踏まえると、物価高による影響が続き、さらに有効な手立てを打てないままだと、倒産件数の減少は期待できません。
自治体の交付金による効果も限定的
2022年9月に、物価高騰への対策として国により「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が創設され、自治体に対する推奨事業のメニューの1つとして、「医療・介護・保育施設、公衆浴場等に対する物価高騰対策支援」が掲げられました。
この仕組みにより、介護施設・事業所は全国各地の自治体において物価対策の交付金を受けられるようになっています。
交付額は施設単位だと数十万円~300万円程度。居宅系サービスだと通所介護で5万円~数十万円、訪問介護は数万円程度のみです。自治体によって対象や交付額はまちまちになっています。
しかしこうした対応による恩恵は限定的というのが実情です。
先の介護人材政策研究会の調査によれば、「すでに交付が決定または交付された」との回答は57.95%。約6割の介護施設・事業所が交付を受けている、もしくはもうすぐ受ける、という状況です。
また、「交付に向けて協議がされている」との回答も17.31%あり、この回答を加えると、7割以上の介護施設・事業所が交付金の恩恵を近いうちに受ける、もしくはすでに受けた、ということになります。つまり介護施設・事業所への交付金の支給は、着々と進んではいるわけです。
しかし先に紹介した通り、こうした交付金の支給が進んでも、「このままでは数年で事業の廃止・倒産に至る可能性がある」との回答が3割近くにも上っています。もちろん、交付金制度によって多少なりとも救われた介護施設・事業所もあるかもしれませんが、その効果は十分とは言えないのが実情です。
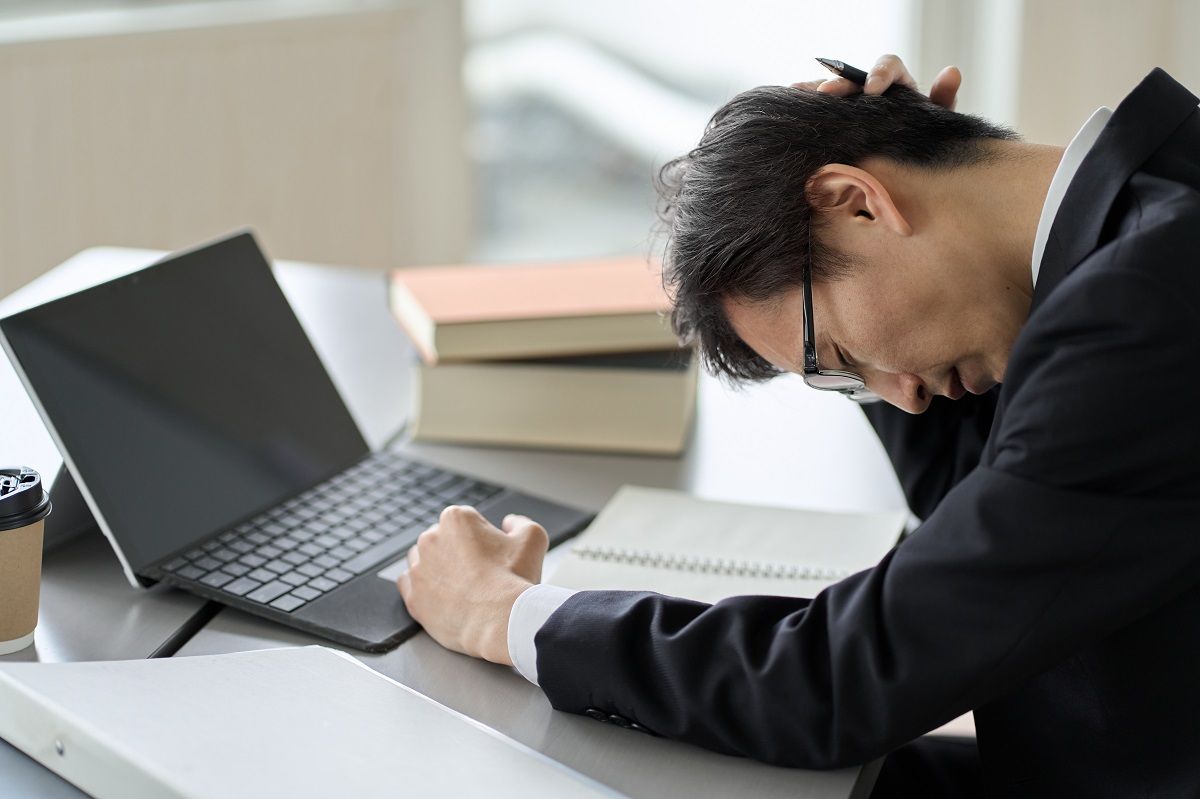
期待される2024年度における介護報酬プラス改定
老人ホームの管理費、食費の値上げも
株式会社TRデータテクノロジーが行った調査(全国の有料老人ホーム6,254カ所対象)によると、物価高騰のあおりを受けて料金値上げに踏み切った老人ホームは23%。値上げ額は平均で管理費5,550円、食費4,460円との結果が出ています。
管理費には水道光熱費が含まれ、食費には各種食材の費用が反映されます。物価が上がっている以上、入居者に求める負担もそれだけ大きくならざるを得ません。管理費と食費の平均値上げ額を合計すると、毎月約1万円の費用増です。年間にすると10万円以上もの値上げ幅です。
さらに有料老人ホームの費用帯ごとに管理費の値上げ額を見てみると、月額費用が10万円未満の施設では8,230円、10~20万円の施設では4,560円、20~30万円の施設では4,620円、30万円以上の施設では8,110円との結果でした。
月額費用が最も安い10万円未満の施設において、特に高額の値上げ幅となっています。
費用が抑えられている施設には、経済的にギリギリの負担で入居している人も多いですが、そうした入居者に管理費だけで毎月8,000円以上もの負担増を強いる形になっているのが現状です。
期待される2024年度介護報酬でのプラス改定
物価高騰が続く中、一般企業では賃上げによる対策が重要視されていますが、介護業界はそれと同じ構図が当てはまらない部分があります。
というのも、介護施設・事業所は一般企業とは異なり、介護サービスに対する報酬額は介護保険制度で定められています。提供する介護サービスの対価を、介護施設・事業所側の判断で勝手に上げることはできないので、物価高への対応はコストカットに頼る面が大きいです。
有料老人ホームなどでは、介護サービス以外の料金を上げて用者の負担を増やすという方法もありますが、あまりに値上げすると利用離れを招くので、対応には限界があります。
コストカットを行う場合、介護施設・事業所における経費の6~7割が人件費であるため、給与現象・賞与カットという形になりやすいです。この点は構造的な問題であるため、国側が物価高騰に対する配慮を行わない限り、介護施設・事業所の経営は厳しい状況が続きます。
そんな中で現在期待されているのが、2024年の介護報酬改定におけるプラス改定です。介護サービスの提供単価が上昇すれば、介護施設・事業所としての収入は多少なりともアップします。逆にマイナス改定になると、物価高騰の中でさらに介護施設・事業所の経営を苦しくさせ、介護職のさらなる待遇悪化を招くことにもなるので、それは何とか避けてもらいたいところです。
今回は一般社団法人介護人材政策研究会の調査結果をもとに、介護業界が直面している物価高騰の実情について考えてきました。介護業界で働く人の待遇をこれ以上悪化させないためにも、2024年のプラス改定を期待したいです。







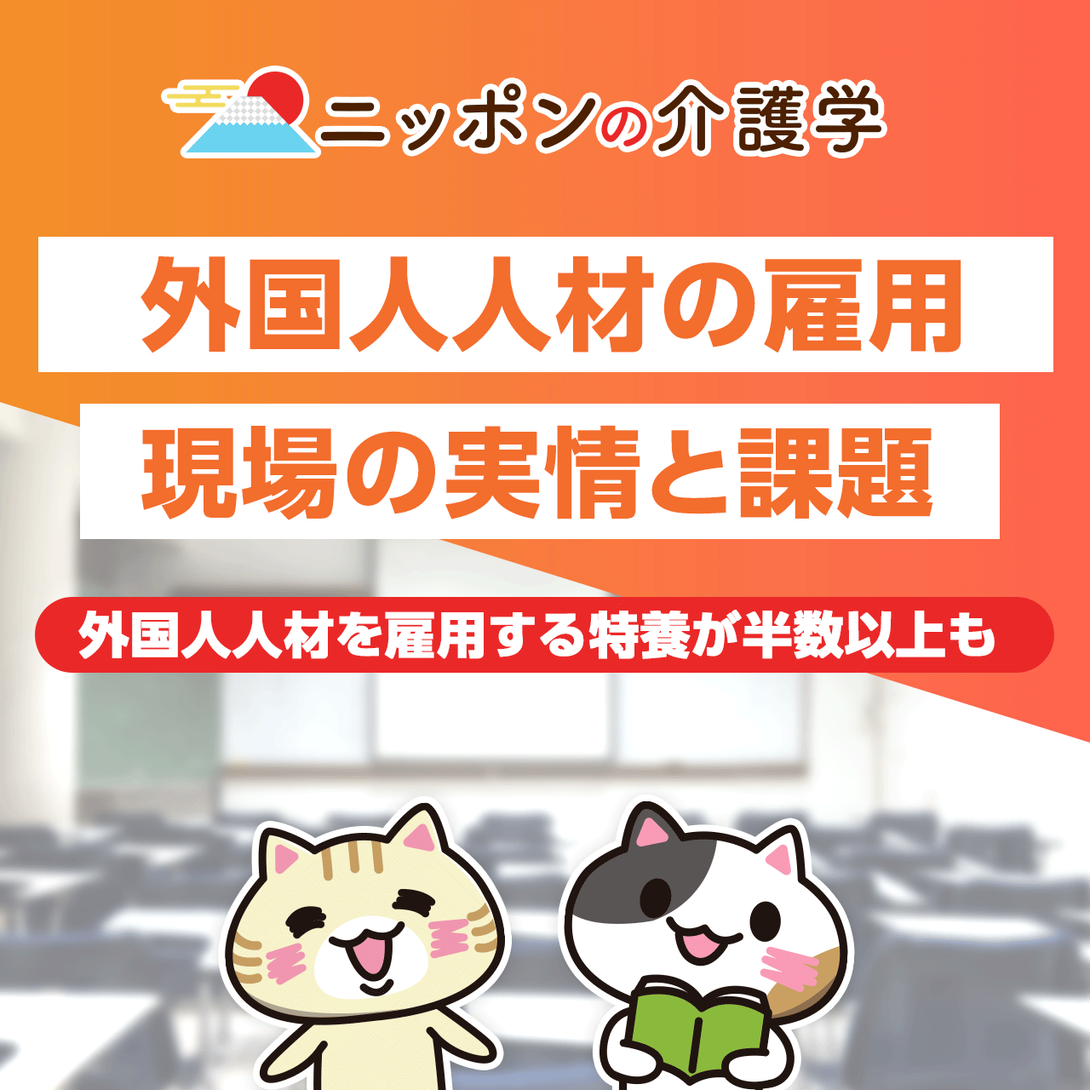
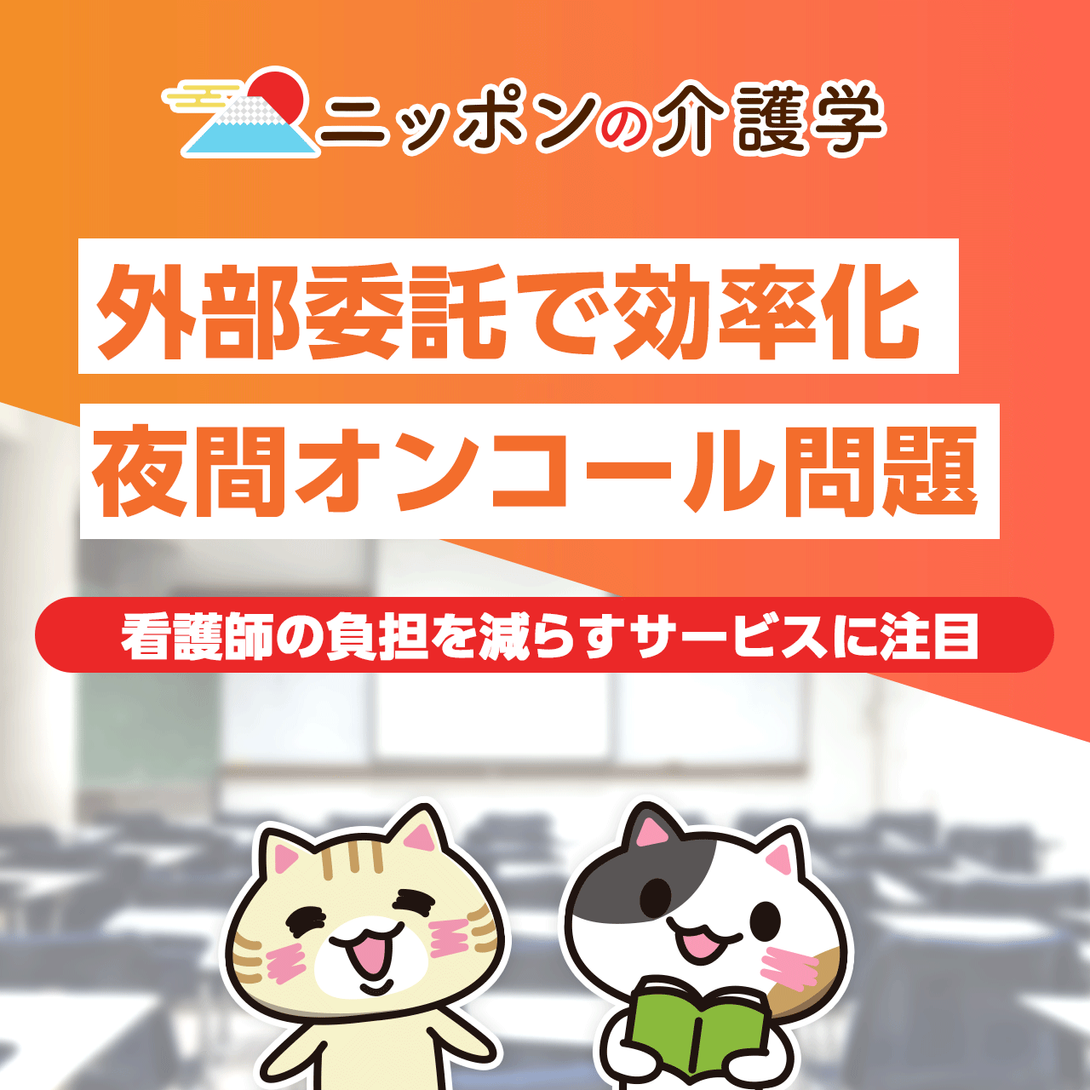
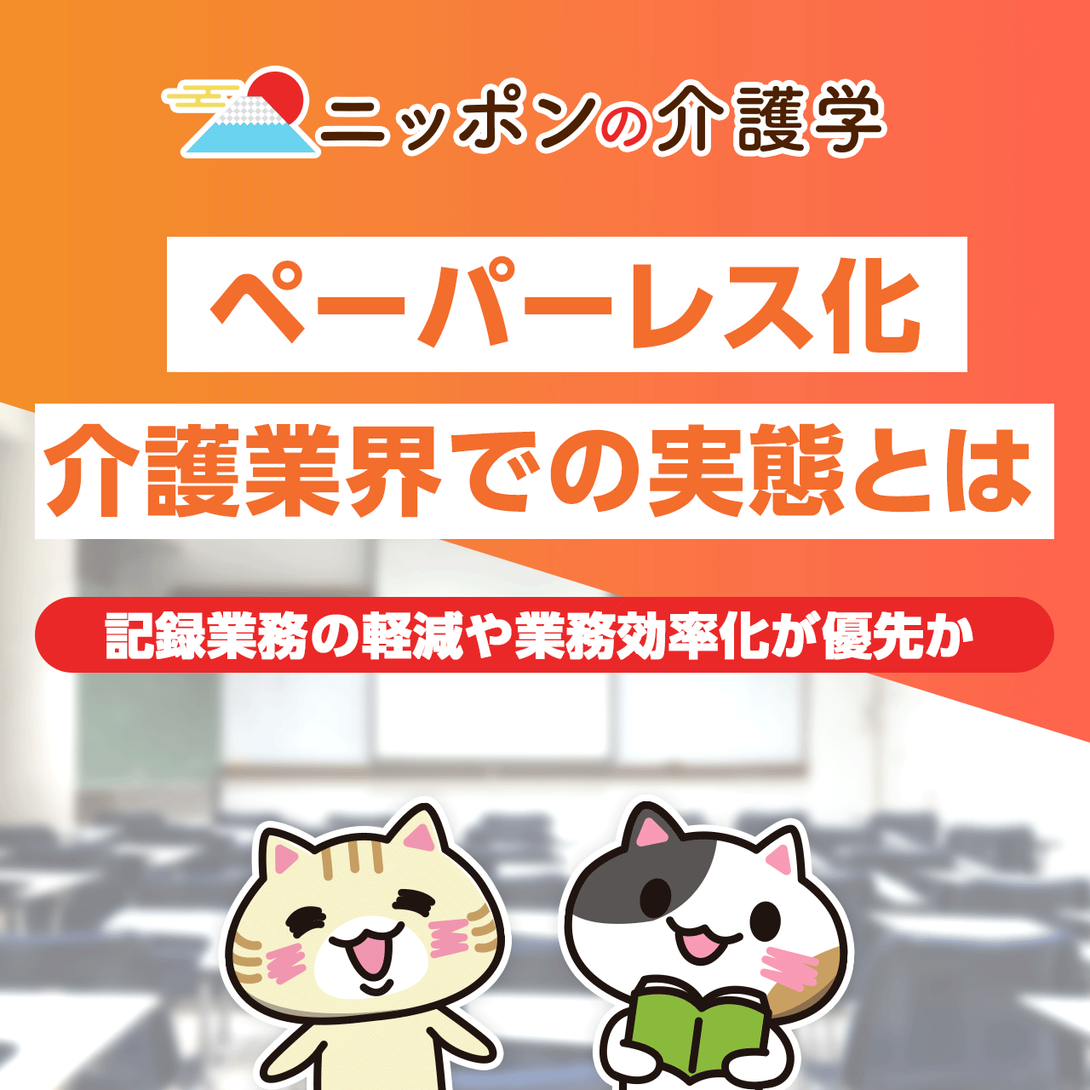

 この記事の
この記事の
みんなのコメント
ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。
投稿を行った場合、
ガイドラインに同意したものとみなします。
みんなのコメント 0件
投稿ガイドライン
コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。
書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。
ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。
当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。
以下のメールアドレスにお問い合わせください。
info@minnanokaigo.com
当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。
2020年9月7日 制定