東京都の理学療法士の求人






























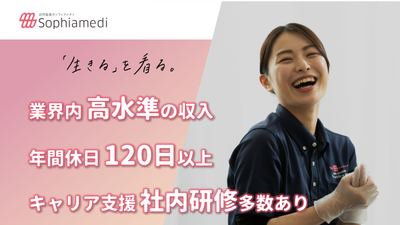























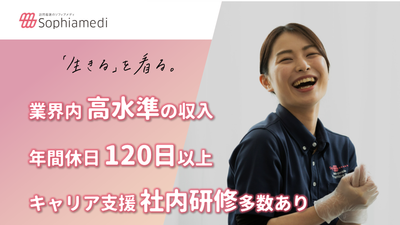



































東京都の理学療法士特集から探す
東京都の理学療法士の平均給与相場
| 市区町村 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| 千代田区 |
283,025円
|
274,950円
|
2,204円
|
2,000円
|
| 中央区 |
414,732円
|
300,000円
|
1,944円
|
1,805円
|
| 港区 |
293,887円
|
293,750円
|
2,117円
|
1,900円
|
| 新宿区 |
297,658円
|
296,557円
|
1,959円
|
1,900円
|
| 文京区 |
293,862円
|
287,000円
|
2,037円
|
1,870円
|
|
東京都の介護求人の平均給与相場をもっと見る
|
||||
東京都の理学療法士の平均給与相場(施設種別)
| 施設種別 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| 居宅介護支援 |
290,848円
|
290,000円
|
1,767円
|
1,800円
|
| 訪問介護 |
276,333円
|
275,000円
|
2,000円
|
2,000円
|
| 訪問看護 |
311,364円
|
300,000円
|
2,310円
|
2,000円
|
| 訪問リハビリ |
277,083円
|
280,000円
|
1,887円
|
1,900円
|
| 定期巡回・随時対応型 |
288,000円
|
288,000円
|
3,000円
|
3,000円
|
|
東京都の介護求人の平均給与相場をもっと見る
|
||||
東京都に隣接するエリアの理学療法士の平均給与相場
| 都道府県 | 正社員 (月収) | パート・アルバイト (時給) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
| 埼玉県 |
265,947円
|
256,971円
|
1,732円
|
1,650円
|
| 千葉県 |
263,987円
|
260,000円
|
1,666円
|
1,540円
|
| 神奈川県 |
274,583円
|
270,000円
|
1,950円
|
1,700円
|
| 山梨県 |
225,838円
|
225,657円
|
1,336円
|
1,300円
|
東京都の理学療法士の動向
東京都の理学療法士の求人数のトレンド
最新の求人数
よくある質問
-
【給与相場】東京都の理学療法士求人の相場はどのくらいですか?
-
【給与相場】
東京都の理学療法士求人の相場は以下の通りです。
「正社員」
平均値:29.0万円
中央値:28.5万円
「パート・アルバイト」
平均値:1,996円
中央値:1,800円
【詳細説明】
居宅介護支援 や ショートステイ などの施設の方が、ほかの施設よりも平均給料額が高い傾向があります。
-
【経験】東京都の理学療法士求人は未経験でも働けますか?
-
【未経験OKの求人数】
東京都の理学療法士で、 未経験可 の求人は1,098件です。
【詳細説明】
東京都の理学療法士では、未経験でも介護現場で充分活躍することができます。
研修制度あり といった条件の介護施設を選ぶことで、働きながらスムーズにスキルアップを図ることも可能です。
-
【年齢】東京都の理学療法士求人には、年齢制限はありますか?
-
【年齢制限なしの求人】
東京都の理学療法士求人で、 40代が活躍 されている求人は 1,474件、 50代が活躍 されている求人は 1,453件、 60代が活躍 されている求人は 289件です。
【詳細説明】
東京都の理学療法士求人では、40代以上で活躍されている求人が多いです。
また、 介護福祉士 や 介護支援専門員(ケアマネジャー) のような資格が活かせる求人であったり、産休や育休などから復帰を考えている方には ブランク可 といった条件の求人もおすすめです。
-
【休日・休暇】東京都の理学療法士求人の休日・休暇日数はどれくらいですか?
-
【休日・休暇】
東京都の理学療法士求人で、 年間休日110日以上 の求人数は200件、 年間休日120日以上 の求人数は237件です。
【詳細説明】
東京都の理学療法士求人では、 完全週休2日 や 週休2日 といった求人が多く、 有給消化促進 や 産休あり といった制度が 充実している求人もたくさんあります。

毎週、希望条件にあった
新着求人が届く!
ご登録内容に基づいて、毎週希望内容に近い新着求人が届きます。

 〜
〜 
































