冬場の浴場で高齢者が亡くなるケースが多い
温度差によるヒートショックが原因のひとつ
入浴を好む日本人。毎日の疲れを癒やして、明日への活力を養うための習慣としている人も多いのではないでしょうか。
ただ、冬の入浴には、あるリスクがともないます。
それは最近、ヒートショックです。温度の急激な変化によって、体に大きな負担がかかる入浴時に起きやすくなります。
日本は海外と比べて入浴中の事故が多いといわれています。年間1万9,000人が入浴中に死亡していると推計もあって、特に65歳以上の高齢者は入浴中の事故の割合が非常に高いのが特徴です。
2016年のデータでは、その年の交通事故による死亡者数3,061人より約1,700人も多い、4,821人の高齢者が入浴中の事故で亡くなっています。
入浴中の事故死は、年々増加傾向にあります。2011年からは交通事故を上回る状況が続いていて、特に入浴時のヒートショックの啓発はメディアを通じて近年継続して行われています。
大きなポイントは、入浴中の溺死者の約90%が高齢者であること。

高齢者がヒートショックを起こしやすいとされるのは、以下のような特徴を持つことが多いためです。
| 1 | 身体機能の衰えによって体温調節力や皮膚感覚が鈍っている |
|---|---|
| 2 | 動脈硬化が進行している |
| 3 | 血圧が不安定である |
| 4 | 障害や持病などで、循環器系や自律神経系の身体的なウィークポイントがある |
外気温が低い冬は寒暖差の影響を受けやすいため、高齢者を中心にヒートショックによる入浴中の事故が起きてしまうのです。
ヒートショックが起きやすいのは入浴時や夜間のトイレ
ヒートショックとは、気温差による血圧の急激な変動で、失神や、脳梗塞、心筋梗塞、不整脈などを起こすことです。
冬場の寒い時期などに、暖房の効いた気温の高い部屋などから、浴室などの気温の低い部屋に移動したとき、急な温度差によって体に負担がかかって起こることが多くあります。
また一般的には、寒い廊下や脱衣所で着替えて浴室に入り、そのまま熱いお風呂に入ることで起きる死亡事故を指します。
このほか、夜間のトイレもヒートショックのリスクが高くなります。トイレに暖房がないと、気温の低い状態で排泄しなければならず、力んだりする際に血圧が急変してヒートショックを起こすのです。
ヒートショックは年齢や健康状態に関係なく、誰にでも起こりうるものです。
深夜や早朝の入浴、飲酒後の入浴、循環器系に影響を与えるような薬の服用後の入浴は急激な温度差の影響を受けやすくなります。そのため、とりわけ高齢者は注意しなければなりません。
老化によって心機能や自律神経のバランスが不安定になっていると、急な温度差によって血圧の変化が起きやすくなります。
体温調節機能が衰えている場合も多いため、体温が一気に上昇すると、血圧が急に下がって意識障害が発生。心不全、意識障害による溺死などを招きます。
8割の人がヒートショック対策をしていない
脱衣所と浴槽内の温度差は32℃もある
ヒートショックは、冬に急増する傾向があります。
その理由は、夏より冬の方が、脱衣所や浴室と浴槽内のお湯の温度の差が大きくなるためです。
冬の脱衣所や浴室の推奨温度は18℃以上とされていますが、実際の室温は10℃くらいです。さらに、お風呂お湯の推奨温度は41℃以下にもかかわらず、寒い季節には夏よりも高めの42度くらいで入浴する人が多くなります。
冬の推奨温度で入浴した場合でも、湯温41℃−室温18℃=温度差23℃です。しかし実際には、湯温42℃−室温10℃=温度差32℃もあります。
夏の実際の温度差を計算すると、湯温38℃−室温25℃=13℃。そのため、単純に考えても冬と夏で19℃もの温度差の乖離があると考えられます。
ヒートショックは、温度差によって身体機能にダメージを与えるもの。当然、夏より冬のほうが室温と湯温の差が極端に開くため、心機能や自律神経系に影響が大きくなり、入浴事故が増えてしまいます。
ヒートショック対策をしているのは調査対象の2割未満
給湯機器などを製造する企業「リンナイ」が全国20~70代の男女を対象に、ヒートショックと生活習慣に関する調査を行いました。その結果によると、ヒートショックになる可能性の高い「ヒートショック予備軍」は、全体のおよそ5割もいることが判明。
ヒートショック予備軍とは、以下のようなヒートショックによる影響を受けやすい人たちのことを指します。
| 1 | メタボや肥満、血圧や心臓など循環器系などの病気を持っている |
|---|---|
| 2 | 自宅の浴室や脱衣所に暖房がない |
| 3 | 熱い風呂が好き |
| 4 | 飲酒後に入浴することがある |
さらに、リスクが高いにもかかわらず、具体的なヒートショック対策を日々の入浴に取り入れている人は約3割、予備軍はより少ない約2割しかいないこともわかりました。
さらに同社が、同様に全国20~70代の男女を対象に調査したところ、ほかにも次のようなことがわかりました。
ヒートショックという言葉が「入浴時の温度差が体に悪影響を与えるリスク」であることはを知っている人は、全体の約7割。
しかし、ヒートショックについて詳しいことや予防法まで理解している人は4割程度にとどまっているのです。
「冬場は温まりたいからお湯を42℃以上にしている」「冬場の浴室は寒く感じる」など、ヒートショックの危険性が迫っている人が多いのが事実です。
調査からも、予防を習慣化している人は2割未満という意識の低さが浮き彫りとなりました。

残り8割の人は、ヒートショックによる入浴事故がいつ起きてもおかしくない条件で、毎日お風呂に浸かっていることになります。
「かくれ脱水」が事故の原因である可能性も
乾燥する冬はかくれ脱水になりやすい
脱水症といえば汗を大量にかく、夏場のものと思うかもしれません。
実は、冬場も「かくれ脱水」と呼ばれ、脱水症状が起こりやすい状態であることがわかっています。
「かくれ脱水」になるのには、以下のような理由が考えられます。
| 1 | 寒さのせいで汗をかかないためのどが渇きづらい |
|---|---|
| 2 | 水分摂取の意識が低くなる |
| 3 | 空気の乾燥で皮膚や呼吸から水分が失われやすい |
| 4 | 暖房で室温が高いため思った以上に汗をかいている |
もし「かくれ脱水」状態のまま、入浴で汗を大量にかけばどうなるでしょう。当然、体内の水分量が低下して血液中の水分も失われるため、血栓ができやすくなります。
とりわけ高齢者は、ヒートショックによって心疾患や脳血管障害のリスクが高まってしまうのです。
千葉科学大学の調査によると、浴場での高齢者の死亡事故はヒートショックが原因だと思われがちですが、実は約9割が入浴中の水分不足による熱中症によるものだったことが判明しました。

また、汗には水分とともにミネラルも含まれます。
ミネラルは、細胞の基礎的な働きを支えて、健康維持に欠かせない重要な栄養素。夏の汗に比べて冬の汗には2倍ものミネラルが含まれています。そのため、日頃の栄養バランスが乱れていれば、さらに体への負担は大きくなります。
つまり、冬の入浴の安全対策では、ヒートショックの温度差を小さくすることと同時に、熱中症予防のための水分・ミネラル補給が必要なのです。
入浴には要介護リスクを下げる効果がある
ヒートショックの危険性を知って、「そもそも冬の入浴を控えればいいのではないか」と考えた人もいるかもしれません。
しかし入浴には、「体を温めて血流をアップする」「新陳代謝を活性化する」「身体の緊張をとって疲労を回復する」「免疫力を高めて自律神経のバランスを整える」「リフレッシュ効果」など、さまざまな健康効果があります。
しかも、高齢者約1万4,000人を対象にした調査で、毎日の入浴習慣がある高齢者は、そうでない人に比べて3年後に要介護になるリスクが29%も低くなっているという結果も出ています。
そのため、対策として入浴を控えるのではなく、ヒートショックや熱中症の原因を知り、的確な行動を摂ることが肝心。それではここで、おさらいしましょう。
ヒートショックを防ぐには、まず脱衣所・浴室を暖めて、浴槽の湯温との温度差を小さくします。そして、熱中症対策として、入浴の前後は水分補給を習慣にしましょう。
飲み物は、ミネラルが豊富で無糖かつノンカフェインのむぎ茶がおすすめです。高血圧、脳梗塞、心筋梗塞など循環器系の既往歴がある人は、積極的にむぎ茶などのヘルシーな飲み物を選んでみてください。
健康のためには、ヒートショックの知識に基づいて対策を習慣化しながら、日々のお風呂を楽しむことが重要です。







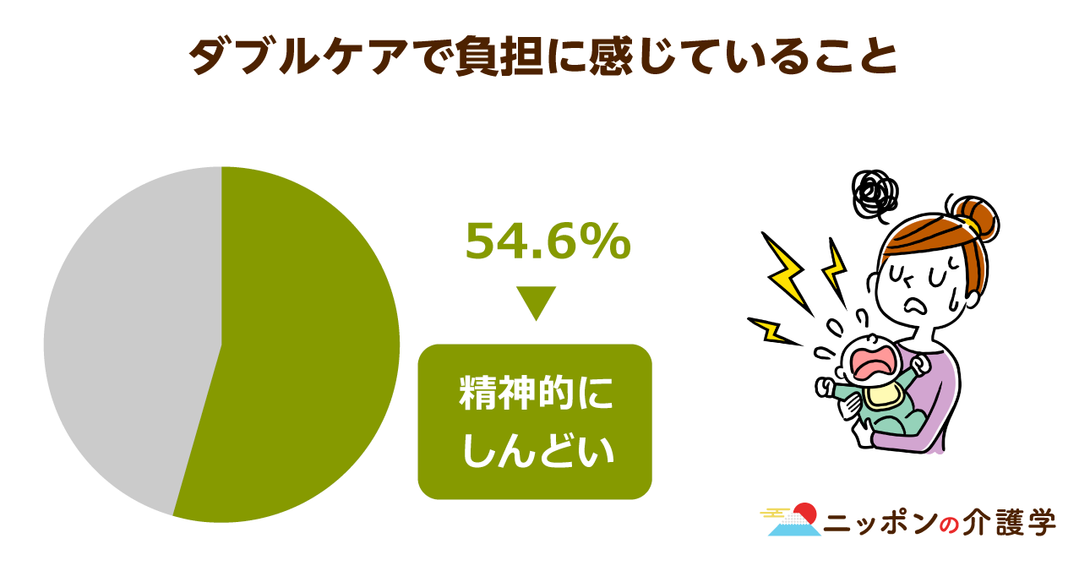

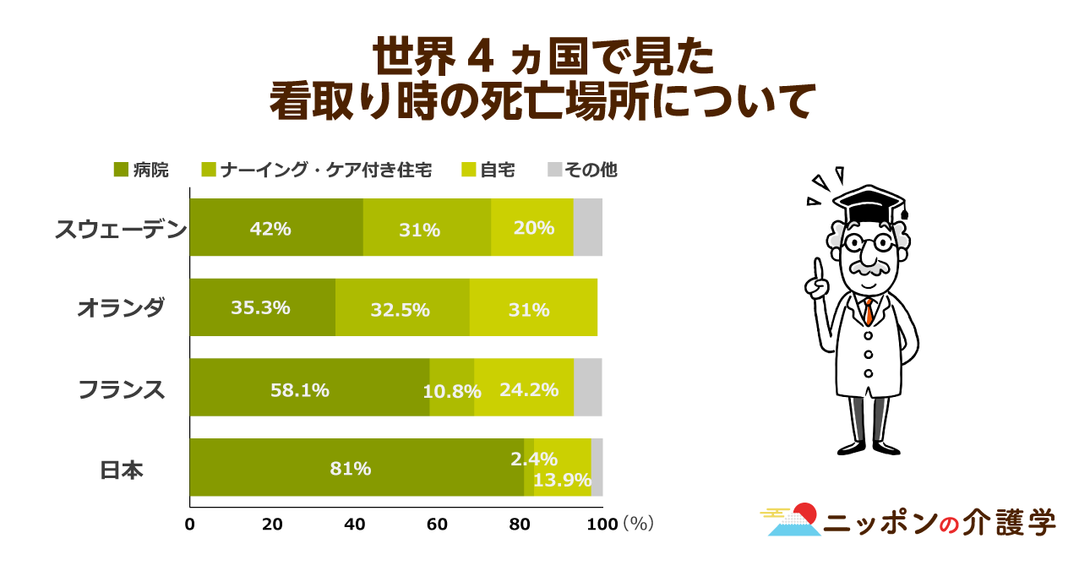

みんなのコメント
ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。
投稿を行った場合、
ガイドラインに同意したものとみなします。
みんなのコメント 3件
投稿ガイドライン
コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。
書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。
ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。
当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。
以下のメールアドレスにお問い合わせください。
info@minnanokaigo.com
当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。
2020年9月7日 制定