日本デイサービス協会が自己負担額2割化に関する調査を実施
自己負担額原則2割化なら、「利用中止・減らす」が約4割
2022年7月19日、一般社団法人日本デイサービス協会が、「自己負担額原則2割導入における利用者意向アンケート」の調査結果を発表しました(2022年5月23~6月5日実施、回答数3,020名、協力事業所255)。
それによると、「仮に、介護保険サービス利用時の自己負担額が原則2割となったら、デイサービスの利用をどうするか」との質問に対して、「利用回数を減らす」との回答は17.8%、「利用時間を短くする」が5.6%、「利用を中止する」が3.9%、「加算サービスを中止する・減らす」が3.1%、「デイサービス以外のサービスを減らす」が7.0%との結果となっています。
これら結果について、デイサービス以外も含めて介護サービスの利用を止める・減らすとの回答を合計すると37.4%、4割近くとなります。

日本デイサービス協会は調査結果の内容を踏まえ、自己負担額が原則2割になることで利用控えが起こり、自立支援に向けた取り組みに影響が出ると指摘。財務省が提案している介護サービスの原則2割化に対し改めて問題を提起しました。
自己負担額原則2割化の議論とは
今回、日本デイサービス協会が上記のようなアンケート調査を行い、その結果を公表した背景にあるのが、2024年度改正に向けた議論が始まる中、「介護保険の自己負担額原則2割化を阻止したい」との意向です。
一律2割化は財務省が主張している案で、実は2021年度の介護保険制度改正で実現するために、2018年からすでに議論が始まっていました。
しかし、2021年度改正では実現せず、財務省としては次回の2024年度改正(介護保険制度改正は3年に1度実施)で実現するために、2割化に向けた議論を今後展開したいわけです。
一方、全国のデイサービスの利害を代弁する日本デイサービス協会としては、先述のアンケート調査結果からも明らかなように、2割化になればデイサービスの利用を「中止する・減らす」動きが強まって、事業所経営にも影響が出ると主張。
2割化による介護現場に混乱を与えないために、財務省の意向に断固反対しています。
財務省による「原則2割化」の提言の背景にあるものとは?
高齢化が進む中、年々増え続ける日本の社会保障費
財務省が原則2割化を目指す背景にあるのが、社会保障関係費の支出抑制による財政の健全化です。
社会保障費とは、年金、医療、介護、子ども・子育ての分野にかかる費用のこと。ここでの「介護」には、財源に公費が投入されている介護保険制度が含まれます。
高齢化が急速に進展する中、年金、医療、介護分野の費用が拡大しつつあるのが現状です。
もともと社会保障制度とは、保険料による支え合いが基本となります。
しかし、現在の日本では高齢者人口が増え、それにともない医療・介護サービスの利用者数の増加も進んでいて、保険料だけで全額をまかなおうとすると、現役世代に負担が集中せざるをえません。
そこで、保険料負担を少しでも減らして制度を維持するために、公費(税金)と公債金(借金)が充てられています。公債金を利用することで、いわば子ども・孫世代に負担を先送りしているわけです。
財務省の資料によれば、国の歳出における社会保障費は、1990年当時は11.6兆円。それが2022年度には36.3兆円と3倍以上に増えています。
現在は新型コロナウイルスへの対策も必要であり、2022年度ではそのための予備費として5兆円が別途計上されています。

そして社会保障費の増大化と連動するように、国の公債金(借金)も増加。1990年度は5.6兆円でしたが、2022年度は36.9兆円まで膨らんでいます。ここ30年ほどで、1年度の公債金額は31.3兆円も増えているのです。
お金の動きを見ると、公債金・借金が膨らみ続ける主な要因は、やはり「社会保障制度を維持するため」にあると言えます。財務省としては、財政を少しでも健全化するために、歳出はできるだけ抑えたいわけです。
介護保険制度の財源は、公費5割(国が25%、都道府県と市町村がそれぞれ12.5%)、保険料5割。現行制度では、介護サービスの利用者には財源から7~9割が保険適用され、利用者は1~3割のみ負担します。
これを制度改正により原則2割化し、財源が7~8割負担、利用者が2~3割負担とすることで、公費の支出の抑制につなげたいというのが、財務省の意向です。
現行制度で2割負担をしているのは5%、3割負担は4%のみ
介護保険制度が開始された2000年当時、介護保険の自己負担額は所得に関係なく一律1割負担とされていました。
その後、高齢化の進展、社会保障費の増大化傾向により、一定の所得のある人を対象に自己負担割合を増やすべきとの議論が浮上。
その結果、2015年度改正において2割負担、2018年度改正において3割負担となる対象者を規定する内容が盛り込まれました。
しかし、2割負担、3割負担となるのは、老後も高水準の所得を得ている人のみが対象です。その結果、実際に2割負担、3割負担を行っている人は極めて少ないのが実情となっています。
厚生労働省の「令和元年度介護保険事業状況報告(年報)」によれば、2019年度における要支援・要介護認定者数の総数は668万6,282人。
このうち、2割負担をしている人は33万8,781人(5.1%)、3割負担をしている人は26万2,676人(3.9%)のみとなります。
つまり、これまでの2割化、3割化の制度改正はごく限られた人だけを対象としたもので、9割以上の利用者にとっては関係のない改正であったわけです。
これでは社会保障費の抑制効果は限られるので、抑制効果を上げるなら原則2割のような抜本的な改定が必要になってきます。
2割負担化の議論は慎重な検討が必要
2割負担にすると懸念されること
日本デイサービス協会が行った調査によれば、「自己負担額が2割となったら利用の見直しを行う」と回答した人にその理由を尋ねたところ、「負担金額が大きい(支払いに困る可能性がある等)」が全体の66%を占め最多回答でした。
さらに、利用回数を減らしたり、利用制限が必要になったりした場合に懸念されることを尋ねたところ(複数回答)、「運動が減るので筋力低下等で調子が悪くなる」(30.4%)が最多回答。
他にも、「外出する機会が少なくなる」「人と会わなくなるので生活意欲が落ちる」などの回答が多く見受けられました。

原則2割化で利用控えが起こると、心身機能の低下が進み、重度化しやすくなることを懸念する声が多いといえます。
実際にそのような人が増えれば、より多くの医療・介護を必要とする人を増加させることになり、社会保障費の抑制効果も薄まってしまうとも考えられます。
「2割負担」は慎重に検討すべき
デイサービスには、利用者の心身機能を維持・向上させ、社会交流の機会を提供するという重要な役割があります。自身の健康を守り、より自立した生活を送れるようにするためにも、要支援・要介護の方は利用を続けることが大事です。
そのため、もし2割化の議論を進めるのであれば、利用控えが起こらないような対策を事前に講じ、「金銭的負担が大きいのでデイサービスを利用できない」という人を生じさせないようにするのが、望ましい保険行政のあり方でしょう。
サポートの仕方としては、2割負担化によって金銭的な支払が困難になる人を対象に、助成制度を策定していくことがオーソドックスな方法ではあります。
ただし、この方法は結局公費投入が必要となるため、社会保障費の抑制効果は薄まらざるを得ないでしょう。
いずれにせよ、2割化の議論は利用者の状況を踏まえながら、慎重に進める必要があります。2割化を推し進めるのであれば、介護サービスが高額過ぎて使えないという事態が起こらないような配慮が求められるでしょう。







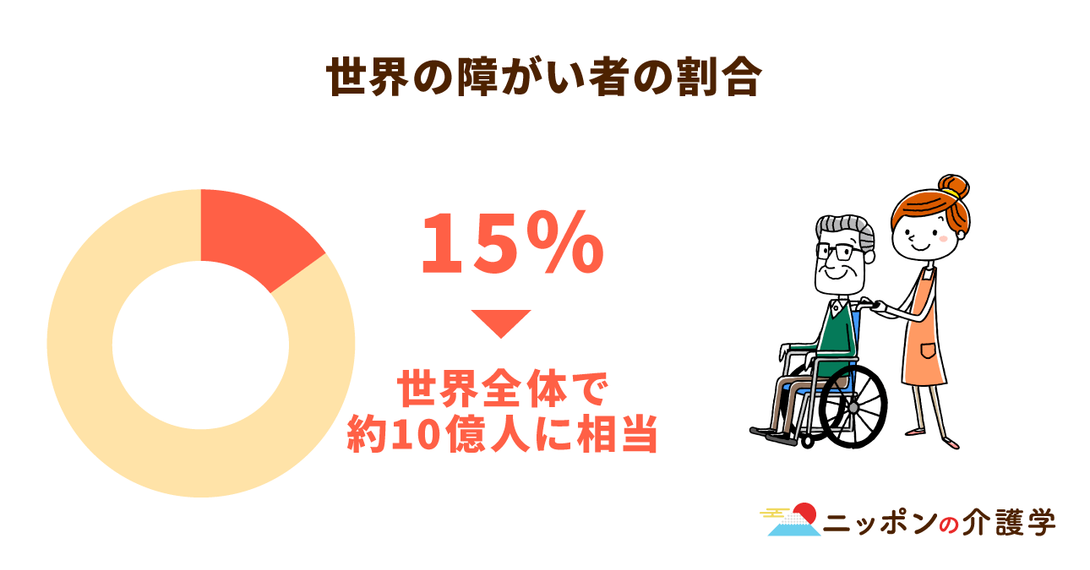

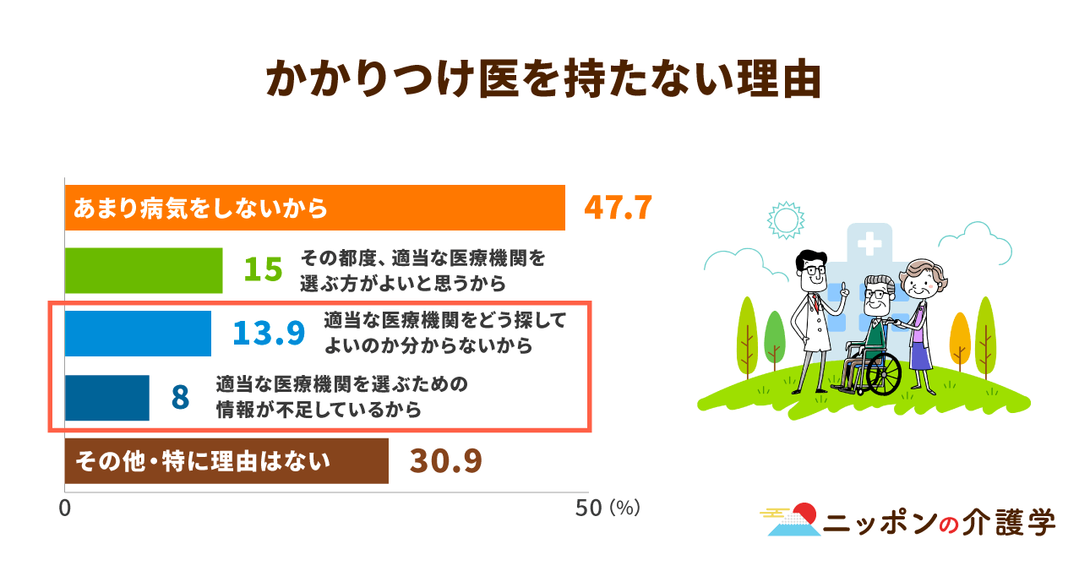

みんなのコメント
ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。
投稿を行った場合、
ガイドラインに同意したものとみなします。
みんなのコメント 0件
投稿ガイドライン
コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。
書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。
ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。
当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。
以下のメールアドレスにお問い合わせください。
info@minnanokaigo.com
当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。
2020年9月7日 制定