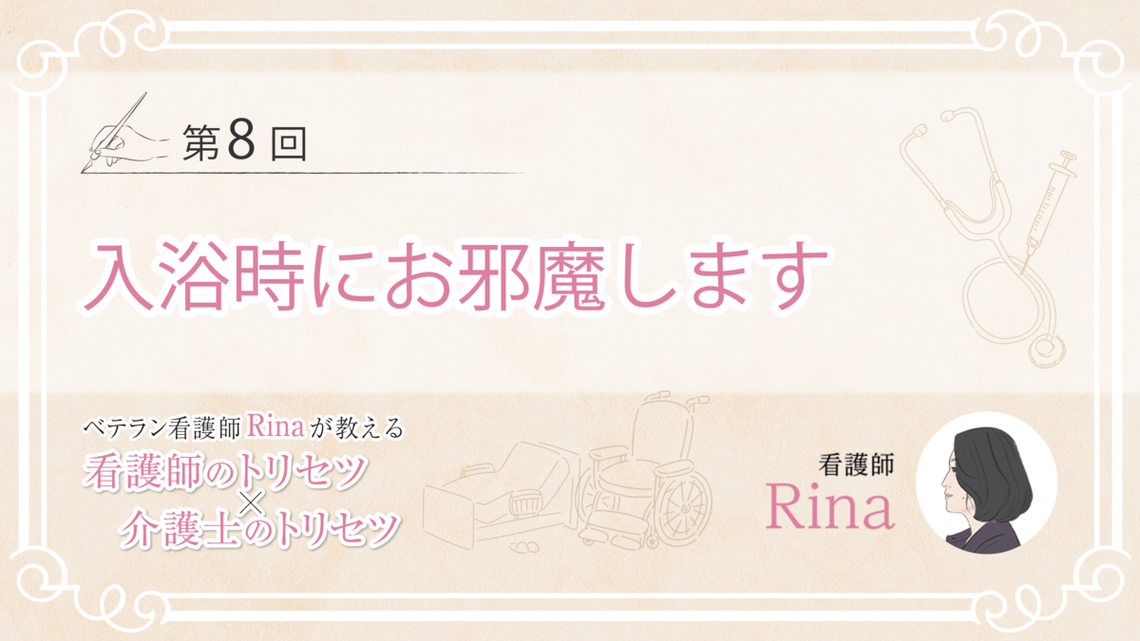接触は優しく
頻回な呼び出し
私が働いている施設では各フロアの担当看護師が決まっています。
担当看護師がお休みの時は、出勤している別の看護師が代わりに担当します。そのため、担当以外の看護師が入っても分かるように医師の指示や処置、薬の情報は一覧表を作成し、看護記録に詳細を記載しています。
だから誰が担当しても対応できる!…のはずですが、記載内容の更新がされていないことが、ままあります。担当看護師は「あれとこれを記録更新しなきゃ」と思いながらも「明日も出勤だから明日の状況を確認してから看護記録を更新しよう。」と考えてしまうことも少なくありません。そういう時に限って、急な受診対応や緊急な処置等で忙しくなり、記載更新ができませんでした……、という事があります。あくまでも看護師同士が情報交換するためなので利用者に影響はないのですが、スムーズに業務を行えないというリスクがあります。……あと、ちょっとイラっとします。
ある日、簡単で効率的な記載方法はないかしら…と思っていたら、今フロアから医務室に帰ってきた看護師のPHSが鳴りました(看護師は全員PHSを持ちます)。
あれ?さっきも呼び出されてフロアに行ってたような?
彼女は「…はい、わかりました。行きます。」と応対しながらフロアへ行ってしまいました。しばらくして帰ってきた彼女に呼び出された内容を聞くと「入浴時の処置で呼ばれました。処置表に書かれていない処置があるみたいで」と疲れた顔をしています。
そこでまた彼女のPHSが鳴りました。私は「うわぁまた?今度は私が行くよ。」と伝え、彼女が担当しているフロアへ行きました。彼女は先週入職した看護師で、その日休んでいる看護師の代わりにフロアへ入ってもらっていました。
フロアの浴室に顔を出すと、介護士より「処置があるのに何ですぐいなくなるの?こっちも連絡の度に作業の手を止めなくちゃならないし、仕事が進まないんだけど。…あれ?違う看護師が来た」としかめ顔で言われました。
私は「あぁそうだよねぇ。連絡する方も大変だよね。私も何でこんな状況になっているのか知りたいから変わって来てみた」と返答し、処置を開始しました。現場に来て分かりましたが、処置表の記載と処方されている塗布剤の内容が違っていたのです。処置が必要な利用者が増えていることもあり、代わりに担当した彼女がまだ利用者の名前を覚えていなかったため、一覧表を頼りに処置をしてしまっていたのです。本来なら担当看護師が更新するべき記載を怠っていたため起こったことだと判明しました。
私は、介護士に業務が滞った理由を説明した上で、本日の入浴者と処置が必要な利用者をチェックし、処置を実施してから浴室を出ました。
季節が変わると処置も変わる
それにしても、処置の追加が多い。なぜだ。
増えた処置は、表皮剥離・かき壊し・皮膚乾燥等でした。あぁ、寒い時期がきたって感じです。冬期は空気が乾燥することに加え、室内の暖房でさらに乾燥します。空調設備による加湿はしますが、まぁ間に合いません(笑)
各居室に温度・湿度計があり、介護士は毎日時間でチェックしています。私も訪室時に確認しますが、湿度計は高くても乾燥を感じることもしばしば。
さらに、高齢者は皮脂が少なく普段から乾燥肌の傾向にあります。そこに乾いた空気が追い打ちをかけてさらに乾燥。皮膚は乾燥すると弱くなり、少しの摩擦や刺激で表皮隔離を起こしてしまいます。トランスや誘導・介助時は要注意です。
季節の変わり目は処置が必要な方が増えたり、内容が変更になったりします。そのため、処置内容の更新が間に合わない!時がある。と、言い訳をしたくなります……。
表皮は皮膚の最も外側にあり、紫外線や外気など外的刺激にさらされている部分です。表皮細胞は、一般的に28日周期で生まれ変わるターンオーバー(新陳代謝)を備え、肌のうるおいを保つ重要な役割を果たしています。
高齢者の皮膚の特徴として挙げられるのが、汗や皮脂分泌の減少。皮膚のバリア機能が低下し、体内の水分が保持できずに皮膚の乾燥が引き起こされ、乾燥が強くなるとかゆみが生じやすくなります。
また、加齢でターンオーバーが低下すると皮膚の弾力性が低下するだけでなく、皮膚の薄くなります。さらに皮膚表面が平坦化して光沢を帯びることも。このような脆弱な皮膚は、傷ができやすく、傷が治りにくいことがあります。
高齢者のスキントラブルの予防は、皮膚の特徴を知り、愛護的なスキンケアの意識をもつことで、皮膚の健康維持につなげることができます。
1.保湿で皮膚を乾燥から守る
・保湿剤の塗布
保湿力のあるのびのよいクリームやローションを1日2回以上塗布します。入浴後30分以内の塗布は、保湿力を高めます。
・入浴時の注意
長時間の入浴や頻回の入浴、熱いお湯での入浴は、皮膚の水分保湿機能の低下につながり、皮膚の乾燥を助長します。お湯の温度は、ぬるめで、保湿成分を含んだ入浴剤などの工夫も必要です。弱酸性の洗浄剤は、皮膚に刺激の少ない優しいケアとなります。
2.刺激の除去と皮膚の保護
・皮膚を強くこすらない
皮膚のバリア機能の低下や乾燥を予防するために、皮膚を強くこすらないことが重要です。洗浄剤の泡を利用して、クッションを滑らせるように優しく洗うことで刺激の低減となります。
皮膚を保護する
手足などの皮膚は、打撲や摩擦で容易に損傷する事があり、衣類などで保護が必要です。また、保湿剤で潤いを保持することで、皮膚の保護につながります。
おむつ使用時は、蒸れで皮膚がふやける場合が多く、バリア機能が低下します。ふやけや汚れによる刺激から皮膚を保護する撥水クリームなどの塗布が必要です。
*筑後市立病院「高齢者のスキントラブルの予防」参照
利用者の入浴時にはスキントラブルのチェックや創部処置をすぐできるように、看護師が介入できる環境が理想的だと思います。しかし現実は人員不足で、処置が必要な時は随時看護師を呼び、処置が必要ない方へは入浴後に介護士から保湿クリームを塗布してもらうなどの対応をしています。
振り返り
処置の効率化
色々な業務に対して統一した対応ができるようにと工夫をしても、それが実際に可動出来るかは別の問題。
入浴時の処置方法ひとつをあげても、個々人の考え方によって違ってきます。同部署内だけの決まりならいいのですが、介護士との関わりが多いため関係してきます。
今回は、まだ環境に慣れていない看護師が対応したため、気が付くことができました。
介護士(夫)より
処置の度に看護師を呼ぶのは構わないが、呼んでもすぐに来ない時は困る。入浴介助の時間は決まっているから、その時間内に終わらせるためには湯舟に5分浸かるところを4分にしたりと調整が必要になってくる。
利用者は週に2回の入浴が決まっている。今日は誰が入るのかを把握して処置をして欲しい。
まとめ
処置一覧表は気を付けて更新していても、記入漏れがありました。そのため、利用者の処置が抜けないように看護師で話し合いをしました。結果、塗布剤が処方された時にチャック付き収納袋に入れて、利用者の名前・薬剤・処置部位・用法・使用開始日を袋に記入しフロアごとの専用ケースに保管。今後は一覧表の確認だけでなく、ケース内を必ず確認して処置を行うことにしました。処置の開始と終了時には看護記録に記入し(勿論、経過も記録します)介護士に申し送りを行いました。
入浴日の朝には入浴する利用者の処置が必要な方をチェックし介護士に呼んで貰うように声を掛けます。介護士・看護師で話し合い、できるだけ処置が必要な方が続けて入浴できるように順番を検討したりしました。
お互いに業務内容を知ることによって効率良く仕事ができればイラつくことだって少なくなります。
介護士からの連絡ですぐに行けない時は、他の看護師に連絡し対応をするようにしました。
同部署でも他部署でもお互いに声を掛け合うことで、良い関係が築いていけると思います。

自分らしい働き方が
きっと見つかる
他の記事を読む
すべて見る